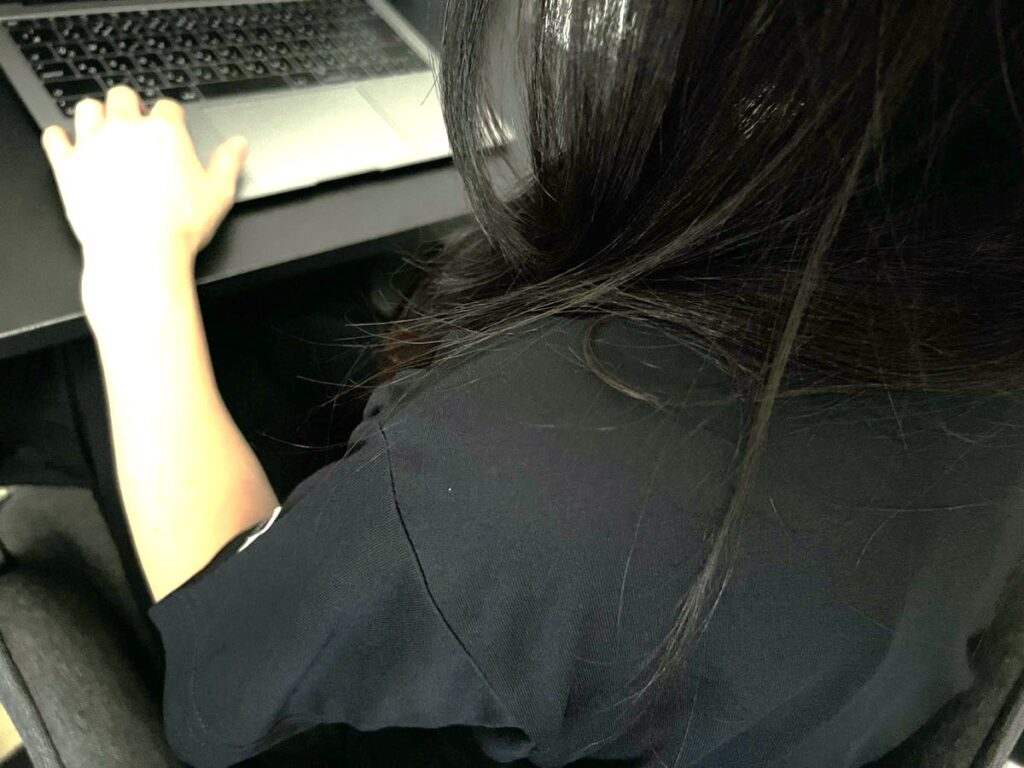Rさんは、就職をきっかけにうつ病を発症。そのときに発達障害と診断されたことで、小さい頃から抱えてきた違和感の正体がわかりました。
山陰地方で育ったRさんは、読書と器械体操が大好きで、海外ペンパルとの文通を楽しむ闊達な少女でした。放課後は友達と遊ぶことも、一人でいることも。自分の心に従って気ままに過ごしました。
友人たちはアイドルやアニメなど共通の話題で盛り上がっていましたが、Rさんは興味を持てず、無理に合わせることもしませんでした。
しかし高校に入ってから、あることに気が付きました。
「私は普通じゃないかもしれない」
全校生徒が20人ほどの小・中学校から、一学年5クラスで200名ほどの同級生がいる環境へ。自分と周囲の違いをより鮮明に体感したそうです。
集団行動が嫌いなわけではありませんでしたが、みんなと気持ちを共有することや調和することができず、どこか冷めて見ているところがあったと振り返ります。
都市部の大学に進学してからは、また少し状況が変わりました。個性的であることが尊重される文化の中で、ゼミやサークルなど様々なグループでのコミュニケーションを経験。社会や集団生活を学ぶ時間になりました。
幼い頃から、両親には『人の気持ちがわかっていない』『思いやりがない』と叱られることも多かったというRさん。
「自分の理論ではよかれと思ってやっていたことが、相手からみたらそうでなかった。子どもの頃は全くわかりませんでした。高校、大学に進む中でいろいろな人に会い、試して、分析して、少しずつうまくやっていく方法を身に着けました」
Rさんは大学卒業後、ある企業に就職しましたが入社1か月で退職してしまいます。
「両親を納得させたい一心で、両親が認めてくれそうな、いいねと言ってくれそうな企業に就職したのですが、実は一番やりたくない職種だった。働くことにちゃんと向き合えないまま、決めてしまい……やはり無理を続けることはできませんでした」
それから改めて就職活動を行い、市役所での再就職が決まりました。公務員として社会に貢献できることが嬉しく、今度こそ頑張ろうという気持ちで挑みました。
しかし、ここでもうまく歯車がかみ合わないのを感じたRさん。
入庁してまもなく、任された大きな仕事を無事にやりとげて周囲から評価されたと思っていましたが、その後仕事を取り上げられるように感じる出来事がありました。
さらに、社会人として至らないと言われることも、人格を否定する言葉をかけられることもあったと言います。
また市役所では電話応対も多く、Rさんもたくさんの電話を取りました。しかし何度やってもなかなか慣れず、相手の話が聞き取れない、間違えた情報を伝えてしまうなど、思うように応対することができません。Rさんは就職して初めて、電話が苦手だということに気付きました。
「相手が何かを求めているのはわかるけど、何を求めているのかがわからない」
はっきりと言ってくれたら理解して行動できるけど、曖昧な言葉や指示では解釈に自信が持てず、Rさんはもやもやと不安を感じます。
次第に職場にいるのが辛くなり、ある時、出社しようと準備を済ませて玄関に向かいましたが、どうしても外に出られない状態となってしまいました。
休ませてほしいと電話をしようとしても、声がでません。何とか話しやすい先輩に連絡をして、すぐに家族に病院に連れていってもらいました。
Rさんは、うつ病を診断されました。さらに発達障害の検査を受けたところ、医師から「広汎性発達障害」という名前を聞かされました。
「これまで両親に言われてきたこと、友達との間や集団の中で感じたことが、なるほど!と理解できました」
3年間休職した後、退職、療養、家族の転勤に伴う転居、離婚など様々なことが重なって、Rさんはしばらく社会や人とのつながりが希薄な生活を送りました。
そんなRさんの転機となったのは、駅で清掃の仕事に就く年配の方を見かけたことでした。
「その光景をみて、私も何かしたい、貢献したい、自立したい、と強く感じたんです」
障害があり、ブランクもある、自分一人で就活をするのは難しい、と考えたRさんは就職サポートについて調べて、初めて就労移行支援のことを知りました。
しばらく人と接することがなかったので、さらに電話に対する恐怖が増していたRさんはメールでのやりとりを希望していることを伝えながら、いくつかWebから問い合わせをしてみます。
しかし、突然電話がかかってきたり、電話でないと説明は難しいという回答ばかり。
「メールでも大丈夫だと言ってくれたのはmanabyだけ。この時にここに通おうと決めました」
この支援員のいる事業所なら、悩みを相談しやすいしちゃんと話を聴いてくれると感じたと言います。
それからRさんは在宅訓練と通所訓練を組み合わせて、就職に向けた準備を始めました。
これまで、人と関わることで傷ついてきたことも多く、次の就職は在宅勤務を目指そうと考えたRさん。何かしらのITスキルがいるだろうと、プログラミング言語のPython(パイソン)やデータ分析の学習に取り組みました。元々分析するのが好きだったので、データアナリストなどの仕事について調べてみたりもしました。
生活リズムを維持することと、自己分析や自己理解に関する訓練は特に注力しました。
これまでは元気な時にがむしゃらに頑張り、翌日は動けなくなってしまう、などということもしばしばありました。
manabyで支援員に報告する中で、ちょうどよいバランスで維持したいと思えるようになり、いまでは週5日フルタイムで働くのに、自分の余力がわかるようになりました。エネルギーの使い方を身に着けたことは、いまの仕事に役に立っていると言います。
支援員との二人三脚で過ごした1年3か月。Rさんは、対話を通してたくさんの大切なことに気付いたと言います。
「支援員は私のことをよく理解してくれていたように思います。私の感じていることや、認知のゆがみについてなど、直接言われたら受け入れ難いようなことを、自然と対話の中で自分から気づけるように促してくれました。」
訓練を経て、ITコンサル会社への就職が決まりました。ひさしぶりの社会復帰でしたが、入社日までeラーニングでパソコンスキルをおさらいしながら、気持ちを整えていきました。
入社から8か月が経った今、Rさんは社内の各部署の事務作業を担っています。データ入力やニュース情報の収集など、業務内容は多岐にわたります。
今ではチーム内のマネジメントを任されるようになり、メンバーが活躍できるようにアシストをするという役割にも挑戦しています。
「働く前にイメージしていたよりも、難しいことをやっています」とRさん。
週3日出社して2日は在宅勤務を行うハイブリッドワークで、バランスよく働くことができています。もともと完全在宅の仕事を目指していましたが、manabyで自分と向き合い職場実習を経験するうちに、「私は誰かと一緒に何かを創りたいのかも。出社して働くのも悪くない」と考えるように。いまの働き方はとてもいい感じだと言います。
Rさんは、manabyの事業所でたくさんの人と関わり、いろいろな相談をしてきました。
「柔らかくて、ウェルカムで、何でも言って大丈夫だと思える事業所です」
軽妙なやりとりで緊張をほぐしてくれるだけでなく、真剣に向き合って言い難いことも言葉を選んできちんと伝えてくれた支援員たち。内容に合わせて、主担当者だけでなくいろいろな支援員に相談することができたとRさんは振り返ります。
事業所に通ううちに、人に対する恐怖の気持ちがほぐれていきました。
「誰かに頼るって、負担をかけてしまうと遠慮してしまいがちですが、相手や周囲にとって『許可』でもあると思うんです」
自分が思うほど相手は負担だと感じていないし、喜んで迎えてくれて、話してくれてありがとうと言われることもある。誰かが人に頼るのを見て、自分もやってもいいんだと気付ける人もいる。誰かに頼ることは、自分が助かるだけでなく他者にもいい影響を与えることも多い。自分が勇気を出して頼ることができたら、今度は自分も他の人に貢献できる。
Rさんは、就労移行支援事業所や今の職場でのたくさんの経験を通して、そう感じているのだと教えてくれました。
「働きたいとか、小さくても何かをやりたいと思っている自分を、まずは褒めてほしいです。そしてほんの少しでも勇気を持ったら、知らなかった新しい世界があるはず。頑張らなくていいから、ちょっとつまみぐいしようというくらいの気持ちで、味わってみたらいい」
(2024年8月取材)